第1章|法人税率と特別税率
各事業年度の所得に対する法人税率の概要
法人税法では、各事業年度の所得に対して原則として23.2%の税率が適用されます。この税率はすべての法人に一律に適用されるものではなく、法人の種類や規模によって異なる取扱いが設けられています。
たとえば、資本金1億円以下の普通法人については、その所得の一部に対して軽減税率(15%)が適用される仕組みがあります。また、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等および特定の医療法人など、法人の性質に応じて異なる税率が用意されており、個別の事情に応じた制度設計がなされています。
このように、法人税率には原則のほか、軽減税率などの特例が併存している点に注意が必要です。
使途秘匿金に対する特別税率
次に、通常の法人税率とは異なる「特別税率」の一つとして、使途秘匿金に対する税率について触れておきます。
この制度は、法人が支出した金銭のうち、その相手方の氏名・住所・支出理由が帳簿書類に記載されていない支出、すなわち「使途秘匿金」に対して、追加的に法人税を課すというものです。
この制度が導入された背景には、社会的モラルや税の公平性を確保する観点がありました。特に、交際費や接待費といった名目での支出が、実際には違法または不当な目的に利用されるケースが少なからず存在していたことが問題視されていたためです。
法人が使途秘匿金の支出を行った場合、その支出額の40%を通常の法人税額に加算するという厳しい課税措置が講じられます。これは、こうした支出を強く抑制するための政策的な対応とされています。
なお、「使途秘匿金」に該当するかどうかは、帳簿書類の記載状況や支出の対価性、金額の妥当性などによって総合的に判断されます。広告物の配布や少額の謝金など、記載がないことに相当の理由がある支出は対象外となりますが、支払金額が不相当に高額であると判断されるような場合は、課税対象に含まれる可能性があります。
特定同族会社に対する留保金課税の特別税率
もう一つの特別税率として重要なのが、特定同族会社に対する留保金課税に関するものです。
同族会社では、少人数の株主が会社を支配している場合が多く、法人に利益を留保することで所得税の累進課税を回避しようとする動きが見られることがあります。これに対して、一定以上の利益を社内に蓄積した場合には、通常の法人税に加えて追加の税率を適用する制度が設けられています。
対象となるのは、「特定同族会社」に該当し、かつ「課税留保金額」が「留保控除額」を超える場合です。
課税留保金額に対して適用される税率は以下の通り区分されています。
- 3,000万円以下の部分:10%
- 3,000万円を超え1億円以下の部分:15%
- 1億円を超える部分:20%
このように、課税留保金額が多くなるほど、高い税率が段階的に適用される仕組みとなっています。
特定同族会社の判定と除外対象
この留保金課税制度の適用対象となる「特定同族会社」の判定についても確認しておく必要があります。
具体的には、株主1グループとその同族関係者(最上位の株主グループ)が、会社の発行済株式または出資の50%超を保有している場合、その会社は「被支配会社」とみなされます。その上で、一定の法人(被支配会社)などを除いた上でもこの条件を満たす場合、その会社は「特定同族会社」として取り扱われます。
ただし、以下のような会社は適用対象から除外されます。
- 資本金1億円以下の会社(資本金5億円以上の大法人の100%子会社を除く)
- 清算中の会社
このように、資本構成や企業形態によって留保金課税の適用可否が変わるため、該当するかどうかの判定は丁寧に行う必要があります。
留保控除額の算定基準
課税留保金額の計算にあたっては、「留保控除額」を差し引く必要があります。
この控除額は以下の3つの基準のうち最も大きい金額とされています。
- 所得等の金額×40%
- 年2,000万円
- 資本金等の額×25%-利益積立金額(当期の所得等の金額に係る部分を除く)
このような控除計算を踏まえたうえで、実際の課税留保金額が求められます。
第2章|税額控除の種類と申告調整
税額控除とは何か
法人税の計算において、税率を乗じて得た税額から一定の金額を控除する制度が「税額控除」です。この制度は、所得控除と異なり、直接税額を減少させるものであるため、その効果は明確に現れます。
税額控除が設けられている目的は大きく分けて二つあり、一つは二重課税の排除、もう一つは政策目的の達成です。前者は個人所得税と法人税、あるいは国内外の法人税の重複を回避するための措置であり、後者は研究開発や設備投資の促進など、特定の経済活動を支援する趣旨があります。
主な税額控除の分類
税額控除は、法令の根拠に応じて大きく以下の2つに分類されます。
法人税法に基づく税額控除
まず、法人税法上に規定されている控除として、以下のようなものが挙げられます。
- 所得税額の控除
法人が利子や配当などの収入を得る際に、源泉徴収された所得税額については、法人税の前払いに相当すると考えられ、法人税額から控除できる仕組みとなっています。控除対象額は、預貯金の利子にかかる所得税については全額、公社債利子や配当にかかるものについては、その元本を保有していた期間に対応する金額となります。 - 外国税額の控除
国外所得に対して外国で課税を受けた場合、その外国法人税額を国内の法人税額から控除できる制度です。この控除を受けるかどうかは法人の任意とされていますが、一部の金額にのみ適用するような選択は認められていません。 - 仮装経理に基づく過大申告への対応控除
過大申告があった場合であっても、その後の更正手続きにより正当な税額が確定された場合には、5年以内の事業年度に対して順次控除を受けられる仕組みが設けられています。
租税特別措置法に基づく税額控除
一方で、特定の政策目標を達成するために設けられた税額控除もあります。こちらは租税特別措置法に基づく制度であり、次のようなものが該当します。
- 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
- 中小企業者等による機械等の取得に対する特別控除
- 特定地域や国家戦略特区における設備投資への特別控除
- 給与支給額の増加に応じた特別控除
これらはすべて、確定申告書に添付された明細書に記載された金額を基礎に計算され、その金額を限度として適用されます。また、対象法人が中小企業者に該当するかどうか、過去の所得金額が一定の基準を超えていないかといった要件も確認が必要です。
特定税額控除については、資本金規模や設備投資の有無などに応じた適用除外規定も存在し、必ずしも全ての制度を活用できるとは限らない点に留意が求められます。
控除対象の税額と損金算入の関係
税額控除によって減額される金額は、基本的には損金の額として算入することができません。特に、所得税額控除や外国税額控除のような二重課税排除目的のものについては、控除額を損金に計上してしまうと、税負担が二重に軽減されてしまう恐れがあるため、損金算入は否定されています。
ただし、税額控除の適用を受けなかった場合、すなわち申告上その金額を控除しないことを選択した場合には、損金への算入が認められる余地もあります。この点は、控除の適否や取扱いを決定する際に実務上の判断が分かれることもあるため、慎重な対応が望ましい部分です。
税額控除と申告調整の関係
税額控除は、法人税の確定申告における任意の申告調整事項とされています。つまり、控除を受けるかどうかは法人が自由に選択することができ、その金額についても、確定申告書、修正申告書または更正請求書に記載された金額の範囲内でのみ適用が可能です。
逆にいえば、申告書等に控除金額が記載されていない場合は、たとえ実態として控除対象となる支出があったとしても、控除を受けることはできません。
特に外国税額控除や租税特別措置法に基づく控除については、申告書類への明細書の添付が必須となっており、かつ「適用額明細書」等の提出も求められています。記載不備や書類の不備がある場合には、控除が否認される可能性もあるため、実務上は記載漏れや添付忘れに対する注意が必要とされます。
第3章|申告書別表四・別表五の機能
別表四の基本的な役割
法人税の申告において、まず中心となるのが「申告書別表四」です。この様式は、損益計算書の当期純利益または純損失を出発点として、各種の申告調整を行い、当期の所得金額または欠損金額を算出するために使用されます。
別表四は、単なる利益計算書というだけでなく、税務上の利益の把握を行う基礎的な資料としての役割も果たしています。すべての法人が申告時に作成しなければならず、その意味で税務実務における「標準書式」としての性格が強いといえるでしょう。
所得金額算出と利益積立金額の基礎
申告書別表四には、大きく2つの機能があります。
ひとつは、企業会計上の数値をもとに所得金額を求める所得算出機能です。これは、確定した利益を出発点とし、税法上の加算・減算調整を行ったうえで、課税対象となる所得を導き出すものです。
もうひとつは、税務上の利益積立金額を計算する基礎となる機能です。この部分では、調整された金額が「留保」なのか「社外流出」なのかといった区分が求められます。とりわけ、当期の利益積立金額を算出する工程においては、この区分が重要な意味を持ってきます。
このように、別表四は単なる調整明細書ではなく、法人税における所得金額と内部留保の算定に深く関わる書類です。
留保と社外流出の区分
法人が計上する調整項目は、大きく「留保」と「社外流出」に分けて整理されます。
「留保」とは、法人の内部に財産が残っている状態を指します。帳簿上は費用として処理されていても、税務上は損金として認められず、その分資産が減らないというケースが典型例です。たとえば、減価償却の超過部分や繰延資産の償却超過、引当金の限度超過などがこれに該当します。また、帳簿に計上されていない売上が判明した場合も、それに対応する売掛金などが留保資産として捉えられることになります。
一方、「社外流出」は、法人の外部に資金等が流出したことを意味します。配当金の支払いや、交際費・役員給与の一部が損金不算入とされた場合などが挙げられます。これらは、税務上の所得には影響を及ぼすことがあっても、実際には資金が社外に出ていっているため、「留保」とは区別して処理する必要があります。
なお、受取配当の益金不算入額のように、所得金額には影響があるものの資金自体は社内に留まるというケースでは、便宜的に社外流出として扱われることもあります。
別表五(一)の補完的な役割
「申告書別表五(一)」は、「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」という名称が示す通り、法人税法上の純資産変動の内訳を記録する様式です。
企業会計上の貸借対照表と法人税法上の計算結果との間には差異が生じることが少なくありません。この差異を税務上明確に把握するために、別表五(一)では利益積立金額や資本金等の額、その異動内容を記載することが求められています。
この書式は、いわば税務計算における貸借対照表の補完資料ともいえるもので、法人税の課税ベースを確定するうえで重要な役割を担っています。特に、利益積立金額は留保金課税の判定や、株式評価の際の指標となることもあるため、その異動内容を正確に把握・管理する意義は小さくありません。
また、別表五(一)には、会計上の「純資産の部」に計上されていない税務上の積立金等についても記載する必要があります。この点を見落としてしまうと、申告内容に誤差が生じることにもつながりかねません。
第4章|税務の不安を相談できるサービス紹介
ここまでの記事を読んで、「制度は理解できたけれど、実際の判断は難しそう」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
そこで本章では、信頼できる税理士と出会えるサービスを2つご紹介します。

申告や制度適用は、最終的には個別事情に応じた判断が必要になります。専門家とつながるきっかけを持っておくだけでも、実務の安心感が大きく変わりますよ。
【1】希望に合わせたマッチングが可能な「税理士紹介申込プロモーション」
こんな方におすすめ
- 今の税理士にモヤモヤを感じている
- 会社や事業の状況に合った税理士を探したい
このサービスのポイント
- ご要望に応じた税理士を無料で紹介(相談は有料)
- 登録税理士はすべて面談・審査済みの実力者
- 法人・個人事業主・相続案件など幅広く対応可能
📌詳細は以下をクリックして公式サイトから確認してみてくださいね(PR)



自分に合った税理士に出会えていないという悩みはよく聞きます。
事前にしっかり面談審査された方だけが登録されているので、信頼性という面でも安心です。
【2】顧問料の見直しや税理士変更に「税理士ドットコム」
こんな方におすすめ
- 顧問料が見合っていないと感じている
- 提案力や対応に不満を感じている
このサービスのポイント
- 利用者の71.4%が顧問料の引き下げに成功
- 「相性が合わない」「業界に詳しくない」などのお悩みに対応
- 中小企業・個人事業主・相続対応など幅広くカバー
📌詳細は以下をクリックして公式サイトから確認してみてくださいね(PR)



税理士に相談しているからこそ違和感に気づくこともあります。
こうしたサービスは、見直しの第一歩として気軽に活用できます。
免責事項
本記事は、税制度に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の税務判断や対応策を推奨するものではありません。
適用にあたっては、必ず税理士などの専門家や信頼できる専門書籍等を確認のうえ、ご自身の判断で対応いただきますようお願いいたします。
なお、本記事の内容を参考にされたことにより生じた損害等について、運営者は一切の責任を負いかねます。
また、本文中には広告を含むプロモーションが含まれている場合があります。あらかじめご了承ください。



皆さまの選択が、より良い方向につながることを心より願っております。
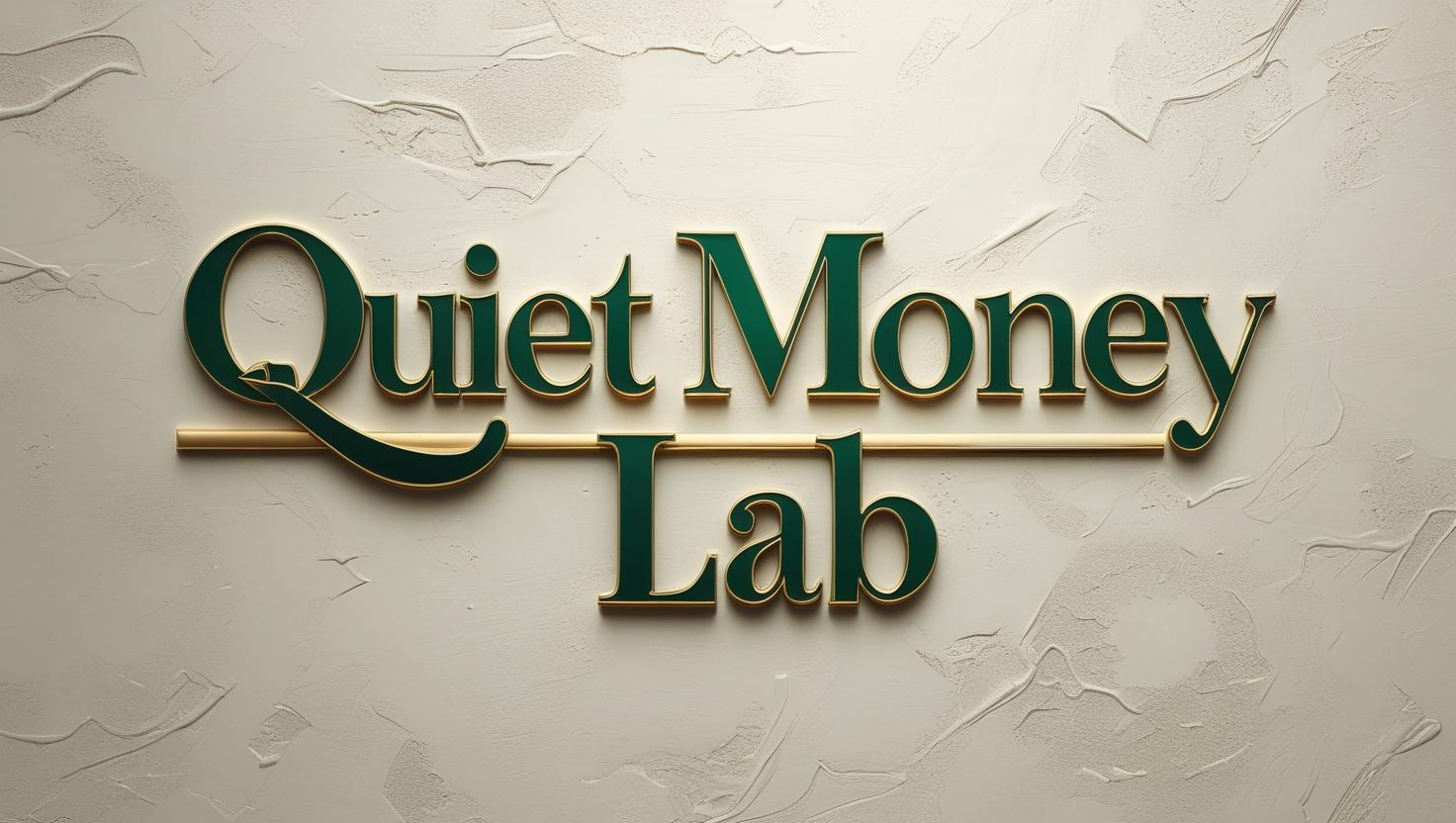




コメント